iDeCo(イデコ)はどんな制度?金融のプロが解説。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、老後資金を自分自身で用意してもらおうと国が税制優遇を設けて後押ししている制度のことをいいます。この背景には、少子高齢化や雇用形態の多様化などの構造的な変化により年金財政がひっ迫している現状があります。年金制度の持続性に疑問符が付く以上、公的年金に頼らない老後資産の準備が何よりも大事になってきます。
今回の記事では厚生労働省の資料を参考に、確定拠出年金制度全体の構造やiDeCoの制度の基礎について、2025年時点で予定されている法改正の内容も含め解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
目次
そもそも「確定拠出年金」ってなに?
日本の公的年金制度は3階建てとなっており、1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金、公的年金の上乗せとして3階部分に私的年金があります。確定拠出年金はこの3階部分の私的年金に該当します。
そして確定拠出年金(DC)とは、掛金を拠出し、自らが運用を指図し、その成果に応じて将来受け取れる年金額が決まる仕組みをいいます。大きくは以下の2つに分類されます。
・企業型DC…一番多いのはこのパターン。企業が制度を設け、原則として掛金は会社が拠出。労使合意のうえで実施
・個人型DC(iDeCo)…個人が任意で加入し、掛金は自ら拠出。運営は国民年金基金連合会が担う
今回は、この個人型DC(iDeCo)に焦点を当てて解説していきます。
iDeCoの基本構造と加入要件
iDeCoは次のような仕組みで成り立っています。
基本構造
1.毎月積み立てる掛金を自分で設定する
2.積み立てた資金を運用する商品を自分で選定(投資信託や定期預金等)
3.原則60歳以降に年金または一時金で受領(途中引出しはできない)
要するに、資産形成の「積立・運用・受取」の選択を、自分自身で判断することを前提とした制度設計になっています。
加入要件
2025年時点での制度に基づく加入要件は、
1.第1号~第3号いずれかの国民年金の被保険者に該当していること(※区分により加入可能年齢は60歳、もしくは65歳まで)
2.老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないこと
なお今後の制度改正により、現行制度では原則60歳未満が加入対象でしたが、近年の高齢就業者の増加を背景に今後70歳未満まで加入年齢が拡大される見通し(2027年ごろが予想されています)です。
税制上の3大メリット
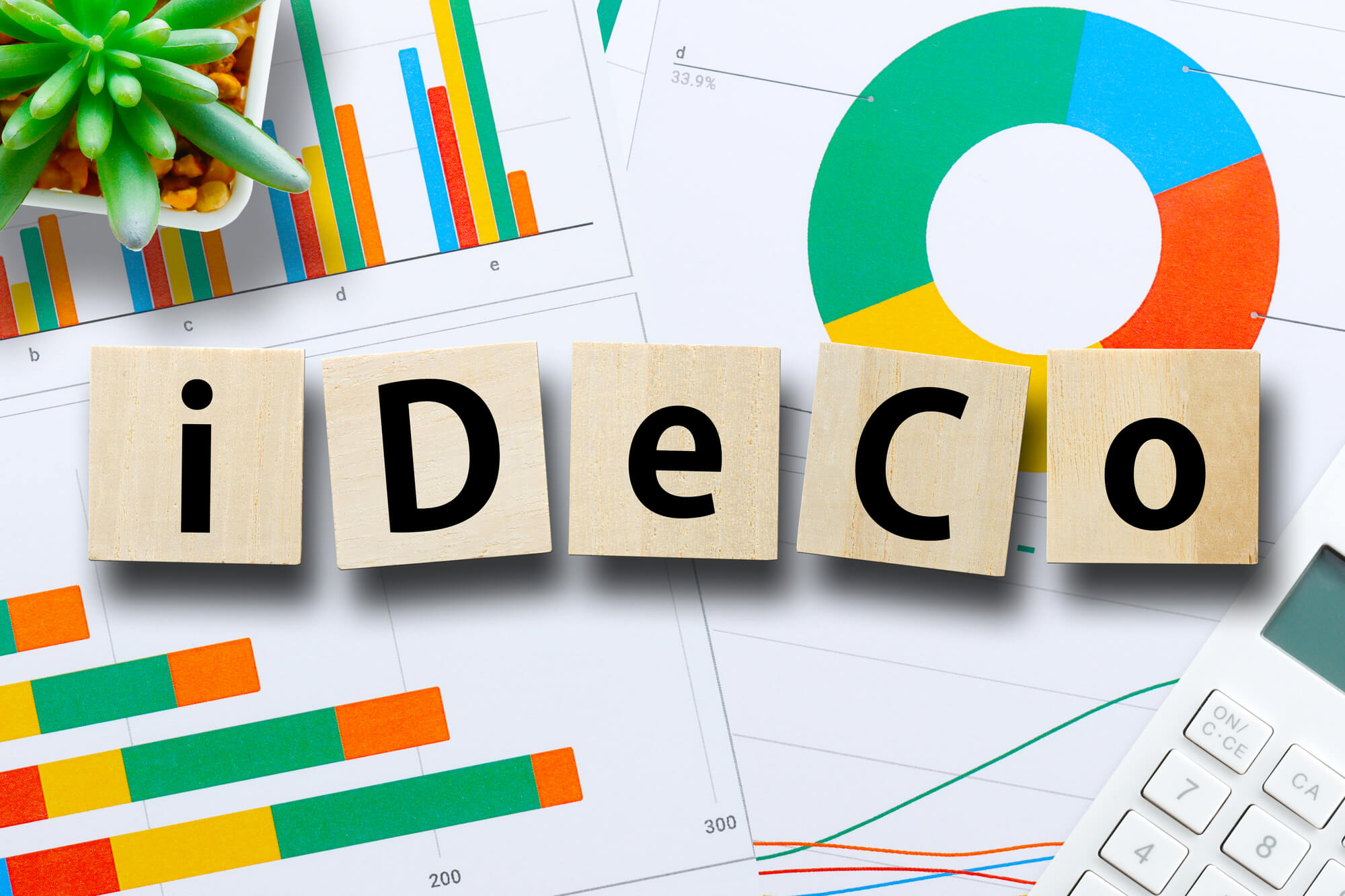
iDeCoを活用する上で最大のメリットは、税制面の優遇措置が法令で明確に定められている点にあります。以下の3点は、どれも制度活用を後押しする合理的な理由といえます。
① 掛金が「全額所得控除」される
拠出した金額が全額所得から差し引かれます。全額控除の対象となることで課税所得が減少し、所得税・住民税が軽減されます。
例えば、年収500万円の会社員が毎月1万円を拠出すると年間で12万円の所得控除となり、税率30%と想定した場合、年間で約3.6万円の税負担軽減(節税効果)が見込まれます。
② 運用益が「非課税」になる
通常、株式・投資信託の運用益(利息・分配金・譲渡益)には約20%の税がかかりますが、iDeCoではこれが非課税となります。非課税で受け取った運用益はそのまま再投資され、複利効果が長期にわたって続くことで最終的な受取額が最大化される仕組みです。
③ 受取り時にも「税制優遇」してもらえる
60歳以降の受取り時には、以下のいずれかの控除が適用されます。
・年金形式で受取る:公的年金等控除
・一時金形式で受取る:退職所得控除
いわゆる「出口」の部分でも税負担が抑えられるよう優遇されています。
制度の「落とし穴」に要注意
iDeCoは税制優遇など制度設計として非常に優れた仕組みではありますが、以下のリスクも制度上明記されており、後から知らなかった…と後悔しては遅いので始める前にしっかりと理解しておきましょう。
1.原則60歳まで引き出せない(途中引き出しができないため流動性が低い)
2.元本保証型以外は運用リスクを伴う(どの商品で運用したとしても運用責任は加入者自身が負う)
3.どの金融機関を選ぶかで手数料負担・運用の選択肢(商品量の多寡)・情報提供の質が大きく異なる(※ランニングコストは運用益から徴収されるので確認必須)
【まとめ】制度をよく理解し、iDeCoを戦略的に使いこなそう!

iDeCoは単なる貯蓄や運用とは異なり、国民が自助努力で長期投資ができるよう国が法的に後押ししている制度です。2025年以降の改正により、加入年齢や拠出枠が拡大されることで、年齢や職業にかかわらずより多くの人にとって柔軟な選択肢となるでしょう。
その一方で、制度の本質を理解せず、与えられたまま使用しても制度本来の効果は得られません。どの金融機関でどの商品を選ぶのか、無理なく毎月拠出できる金額はいくらなのか、利用者自身が主体的にしっかりと考えることが老後に向けた資産形成において何より大事になるでしょう。
けれど、「今まで資産運用の経験もないし、自分の経済状況でどのくらい拠出できるのか分からないから一緒に考えてほしい」とお悩みの方もいると思います。そんな方に、IFAという選択肢をご紹介します。きっと、最初の一歩を踏み出すお手伝いができる存在になります。
IFAとは

IFAとはIndependent Financial Advisorの略で、近年業界で注目を集める金融アドバイザーの業態の一種です。
大きな特徴は、既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスができる事業形態にあります。
まだまだ認知度が低く分かりにくいため下記に特徴を紹介します。
顧客に寄り添った提案が可能
先述の通り、多くの証券会社や銀行の営業マンは会社に所属しているため、目標やノルマがあり、更に会社の方針に従う必要があります。そのため、真に顧客のための営業活動ができないことが予想されます(実際そうだと思います)。
一方、大半のIFA法人は既存の金融機関と資本関係はなく、提携する証券会社や金融機関から販売要請やノルマを課されることがないため、顧客のメリットを最優先した提案が可能です。
豊富なサービスラインナップ
IFA法人は複数の証券会社や生命保険会社等と提携しているケースが多く、それらの豊富な商品ラインナップから顧客に最適なものを提案できる強みがあります。
さらに、税理士や弁護士といった士業と外部連携をしていたり、不動産など金融以外の経験を有していたりと、金融以外の分野にも精通した資産運用全般に長けたIFA法人もあります。
さいごに
outperformに所属するIFAはトータルでお客様のライフプランニングができることを強みにしています。「生涯にわたる資産運用アドバイザー」として、あなたに最適なご提案をさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
(出典資料)厚生労働省「第37回社会保障審議会企業年金・個人年金部会 2024年11月8日 資料①i DeCoの加入可能年齢・受給開始可能年齢」「iDeCoパンフレット」
- 資産運用の相談先は銀行?証券会社?「IFA」という新たな選択肢について
- 債券投資の役割再考。株高の今だからこそ考えたい「クッション」としての価値
- 自社株評価を通じて相続対策を整理できました。
- 結婚を機に、将来に向けてしっかり準備することが出来ました。
- リバランス(資産の再配分)について
- 遅すぎることはない40代・50代からの資産形成。人生後半戦を豊かにする「守り」と「攻め」の戦略
- 保険は「安心を買うコスト」、投資は「資産を育てる種」。家計におけるバランスの黄金比
- 「長期・分散・積立」だけで大丈夫?市場変動に動じないためのメンタル管理術
- 銀行・証券会社・IFA。それぞれの「構造的な違い」と使い分けのポイント









